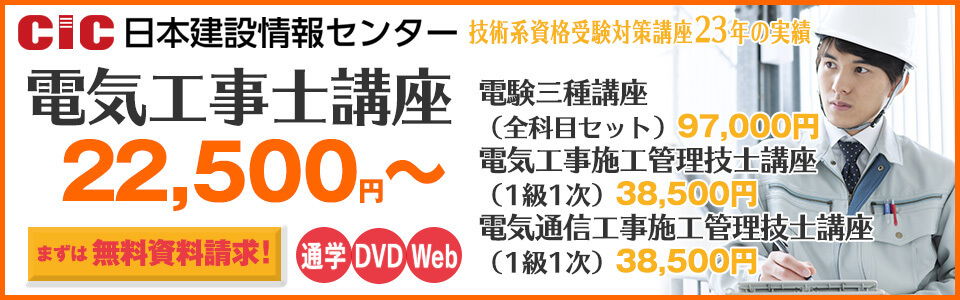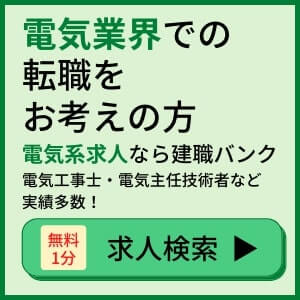電気工作物の保安管理を行うため、電気事業法により定められた国家資格保持者電気主任技術者は今もどこかで電力供給の安定化のために頑張っています。電気の安全を守る重要な役割を持っているのが電気主任技術者です。
そんな電気主任技術者は電気工作物の保安管理を行うために電気工作物ある所に選任されます。ですが、いまいちその選任範囲や選任方法、選任要件などはわかりにくいといわれるものです。今回の記事では電気主任技術者の選任要件などについてを紹介します。
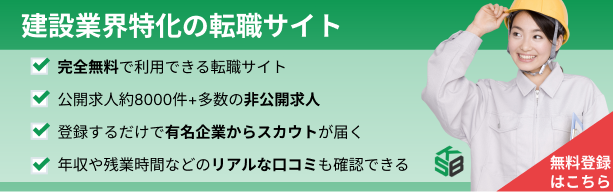
電気主任技術者を選任の意味とは?条件は?
事業用電気工作物における選任でその保安を行うこと

事業用電気工作物とは?(出典:経済産業省HP)
事業用電気工作物は電気事業い使用するための電気工作物のことを指すとされています。事業電気工作物は左の経済産業省の電気工作物の分類画像を見るとわかるのですが、比較的大きな発電所、大工場、自家発電設備、変電所、送電線、配電線などを指します。
事業用電気工作物の中には自家用電気工作物と事業の用に供する電気工作物の2種類の分類があります。
事業の用に供する電気工作物というのは電力会社が使用する発電所を指します。例えば、火力発電所などです。
自家用電気工作物というのは高圧、特別高圧で受電する電気設備を指します。例えば、電力会社から送られた電力を降圧し変電するキュービクルは有名です。受変電設備については☞「受変電設備とは?どんな仕組み?」電気設備については☞「電気設備の基本」
具体的には自家用電気工作物というのは以下のように定義されています。
| 分類 | |
|---|---|
| 1 | 特別高圧(7,000ボルト以上)で受電するもの |
| 2 | 高圧(通常6,000ボルト)で受電するもの |
| 3 | 構外にわたり電線路を有するもの(受電のための電線路を除く) |
| 4 | 発電設備(非常用を含む)を有するもの |
| 5 | 火薬類を製造する事業場、危険なガスを発生する石炭鉱山などに設置するもの |
これに該当する電気設備を保有する事業所は電気主任技術者を選任しなければなりません。明確には電気主任技術者は1~3種がありますので選任する際は電気工作物の電圧の規模と1~3種の扱える電気工作物の範囲を知っておく必要があります。
電気主任技術者が選任される条件
電気主任技術者が事業所に選任される条件となるのはまさに電気主任技術者の免状交付を受けていることになります。電気主任技術者の免状を取得するには、試験で合格するか、認定で面接等を経て取得するかの2パターンあります。そののちに免状申請を行います。詳細な電気主任技術者の免状交付の条件は☞の日本電気技術者検定で確認できます。https://www.jeea.or.jp/electrician/proceeding.html
電気主任技術者の選任に関する法律
電気事業法42条での定め
基本的に電気設備の保安は「自己責任原則」、「自主保安体制」の2つの原則で成り立っています。
具体的な法律の条文では、電気事業法42条で事業用電気工作物設置者において「保安規定の作成と届け出・遵守」の義務が定められていています。
?電気事業法42条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条のニ第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあっては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
電気事業法条42条をかいつまんで要約すると、事業用電気工作作物を保有する事業所はその電気設備に関する保安規定を作成し、経済産業省に届け出をしなければならないのです。電気保安に関する基本原則は「自主保安」にあります。
保安規定の内容
電気事業法条42条で出てくる保安規定の内容は電気事業法施行規則第50条により以下のように定められています。
| 保安規定の内容 | |
|---|---|
| 1 | 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 |
| 2 | 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 |
| 3 | 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 |
| 4 | 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 |
| 5 | 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 |
| 6 | 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 |
| 7 | 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 |
| 8 | 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 |
| 9 | その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 |
電気事業法43条の定め
そして43条で主任技術者の選任義務が定められています。電気主任技術者が選任されるということは事業用電気工作物の保安監督の義務、適切な職務を行う誠実義務の二つの義務の元に選任されるということなのです。
?電気事業法条43条
- 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
- 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
- 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
電気保安に関する知識と経験、そして誠実性をもってして事業用電気工作物の保安管理を法律に基づいて行うのが電気主任技術者です。そして電気主任技術者は電力のライフサイクルの中で必ず選任されています。
ただ、電気主任技術者の資格の区分は三種類あり1~3種とあります。それぞれ正式には漢数字で第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者との区分がなされています。この区分の違いによって選任され扱うことのできる事業用電気工作物の範囲が異なります。その違いは以下の用になります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一種 | すべての電気工作物 |
| 二種 | 電圧170,000V未満の電気工作物 |
| 三種 | 電圧50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く) |
電気主任技術者を選任する届出内容と届出時期
実際に経済産業省に届出をする際には上記の保安規定関連書類と主任技術者関連書類を遅滞なく届出する必要があるのです。
主任技術者関連書類に関しては届出書か申請書かによって異なります。『主任技術者の選任又は解任届出書』は、設置者が選任した後遅滞なく届出しなければなりません。一方、『主任技術者兼任承認申請書』、『主任技術者選任許可申請書』は、事象発生時速やかに申請しなければなりません。
新規で保安規定を届出する際の期限は、届出時期は現場の工事に着手する時点ではすでに工事の監督を必要とし、特に工事計画の手続を必要とする場合には、工事計画の作成にも携わる必要があるので、これらを考慮し、工事着手前の相当な期間において選任し、選任後遅滞なく届出する必要があるのです。
保安規定の変更に関しての届出時期は新規が事業用電気工作物の使用開始前までなのに対して、変更後遅滞なく届出する必要があります。
これらをまとめると、届出時期は以下のようになります。
| 届出内容 | 届出時期 |
|---|---|
| 『主任技術者の選任又は解任届出書』 | 設置者が選任した後遅滞なく届出 |
| 『主任技術者兼任承認申請書』及び『主任技術者選任許可申請書』 | 事象発生時速やかに申請 |
| 『保安規程届出書』 | 事業用電気工作物の使用開始前 |
| 『保安規程変更届出書』 | 変更後、遅滞なく届出 |
ここで出てくる遅滞なく選任届出をするということは、法律用語で約20日から1カ月以内とされることが多いです。
電気主任技術者の選任における例外規定
| 電気主任技術者選任に関する例外規定 | 概要 |
|---|---|
| 電気主任技術者の兼任 | 電気主任技術者は、受電単位で1事業場1主任技術者を原則としているが、やむを得ない事由 により事業場の専従者の中から主任技術者を選任できないときは、所轄の通産局長の承認を得るこ とにより、他の事業場の主任技術者を当該事業場の主任技術者として兼任させることができる。 |
| 電気主任技術者の不選任 | 下記の事業場にあっては、(財)関東電気保安協会又はその他の公益法人に所属する電気管理事務所との間において電気保安に関する業務契約を締結し、通産局長の承認を得れば主任技術者を選任する必要はない。 ・最大電力1000kw未満の発電所 ・出力500kw未満の発電所 ・低圧配電線路の管理事業所 |
| 電気主任技術者免状の交付を受けていない者の選任 | 下記の事業場にあっては、免状の交付を受けていない者であっても、通産局長又は通産大臣の許可 を受けることにより、その者を主任技術者として選任することができる。この主任技術者を“許可主任技術者” ・最大電力500kw未満の需要設備 ・出力500kw未満の発電所 ・1万V未満の変電所 ・1万V未満の送配電線路の管理事業所 |
こちらは関東電気保安協会の定める例外規定となっています。参考
例外規定で出てくる「兼任」にもまた、兼任条件が付与されています。
電気主任技術者の兼任条件
兼任というのはまさに電気主任技術者免状取得者が複数個所の事業所での電気設備の保安業務を行うということですが、兼任するための条件は以下のようになっています。
| 条件 | |
|---|---|
| 1 | 兼任できる事業場数は常勤場所を含めて6カ所以内。 |
| 2 | 電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。 |
| 3 | 同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の要件を満たす契約を締結していること。 |
| 4 | 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。 |
| 5 | 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。 |
これらの条件(参考)に合わせて、事業所の最大電力が2000kw未満の場合が求められます。
電気主任技術者の選任場所:活躍の場
それぞれの電気主任技術者の区分(1種、2種、3種)の違いによって選任される場所は異なってきますが、電気主任技術者が選任される職場は大まかに以下のような工場、ビル、商業施設、鉄道、発電事業所などの場所で選任され活躍しています。
電気主任技術者はこうした施設にある電気設備の保守・点検などの業務を行うのです。電気主任技術者は電気事業法43条に定められているような義務を負って仕事をするのです。
このような施設等にある電気設備での保安管理を行うのが電気主任技術者なのですが、電気設備には自主保安が原則となっています。それゆえに電気主任技術者を常駐させることが安全面で望ましいとされています。常駐として電気主任技術者を採用したい企業のニーズもありますので、職業としての電気主任技術者は引く手あまたともいえます。